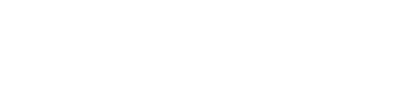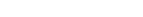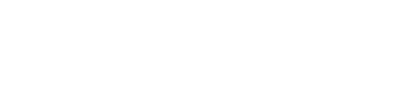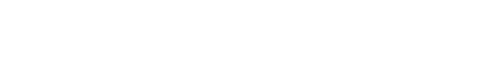スペシャルインタビュー:
木魚職人・加藤寿和さん
(取材・写真:内山洋樹/2019.9.3)
※JPC会報No.162より加筆して転載

仕上げ・音付け・飾り彫り。
K:さて、次は外側をきれいに丸めて行くんですね。この作業はなんて言うんですか?
加藤:う〜ん….. 考えた事無いな(笑)工程としては全体に機械の回転式のサンダーでヤスリをかけて、細かいところは手作業で擦ったりして仕上げて行きます。まあ「仕上げ」と呼ぶしか無いですね。
この二つを見比べると、あっさりこの状態になっちゃうように見えますけど、実はここに行くまでには結構手間がかかってまして。ノミとカンナを駆使してやっとここまで行くんですよね。 で、ここまで切った面が細かくなってくると、やっとヤスリで擦るだけで奇麗に丸いカーブが作れるんです。
K:なるほどなるほど。なんと言うか…多面体をどんどん細かくして行く作業…と言う感じかしら?
加藤:簡単に言うとどんどん角を落として行くって感じですかね。そしてこの後が、音を作って行く作業。そうですね。「音付け」って言ったりします。
K:音付けのときにはどんな事に注意をされていますか?
加藤:普段の木魚の製作では音程は気にしていないものですから、「いちばん響く状態で止める」事になりますね。重要なのは中彫りに加えて、切り込みの端の部分を薄くしたり、深く彫ったりすると音程が下がるんですね。この部分(開口部の端の方)をね、少し指で塞いだり開けたりすると音程や音質が変わるんですが、この工程を進めて行くと、開け閉めをしてもそんなに音に 変化が無くなる状態になる所があるんです。そこまで来ると「あ、ここが限界なんだな」とわかるんです。 そして、この部分をさらに彫ったり薄く削ったりすると、指で塞いだときの方が音が良くなってしまう事があるんですが、そこまでやっちゃうと私どもは「音が抜ける」っていうんですが…
K:あ、それ、「やっちゃった」ってことですか?
加藤:そう、ああ〜、やっちゃったっていう(笑)
K:でもこうやってちゃんと「音付け」された木魚はきちんと「音が人の手で作られた」っていう感じがありますね。素直に鳴るっていうか。
そして最後に飾り彫りですね。飾り彫りの模様にはいくつかスタイルがあるように見えますが。
加藤:はい。この模様は…よく仮面ライダーとか呼ばれてますが(笑)、これが基本的なスタイルです。描かれているのは2頭の竜で、「名古屋彫り」と呼んでいます。小さいものや安価なものには、この「名古屋彫り」の簡略化された「並彫り」のデザインを彫りますが、大きいものや高級なものには造作も精緻に、細かくなっていきます。最高級のものには簡略化を一切排した「龍彫り」を施します。
K:こういうシンメトリーな模様じゃないのもたまに見かけるのですが。
加藤:ああ、あれは「鯱彫り」と言って、「鯱」と言っても実在の鯱ではなくて、架空の魚ですね。「シャ チホコ」の鯱みたいな。京都の方にはこのデザインが多いと聞いた事があります。ウチの工房ではこれは「番外編」みたいな扱いですね。注文数も少ないです。
K:面白いですね。こういったデザインを彫るときは、どんな手順で進めるんですか?
加藤:始めはフリーハンドで絵を付けて行きます。ノミの“R”を使って絵を彫り込んで行く感じですね。 込み入ったデザインになって行くと型紙があるので、それを転写して進めて行きます。
K:始めはフリーハンド!スゴいですね。型紙は型彫り師の方とかが居るんですか?
加藤:それは我々が自分で描きますね。その書き方も一応師匠筋というか、流派みたいなものがあって、 三系統くらいあったそうなんですが、今はもうどんどん廃業されて行くので、実際どの程度残っているかはわかりませんね。
K:なるほど。日本の製造業は、あらゆる業界で慢性的に継承者不足に悩まされている現実がありますね。こういう話を聞くのは、私たちにも辛いものがあります。
加藤:以前は木魚の製造組合があったんですが、ずいぶん前に解散してしまいました。なので業界のようなものはないんです。
でも最近になって、経済産業省から「尾張仏具」という括りで伝統工芸品指定の認可が下りまして。私も「伝統工芸師」と正式に名乗る事が出来るようになりました。こういうことが我々の持っている文化や伝統を残していくのに役に立てばなと思っています。
K:良い方向に向かうことを願っております。